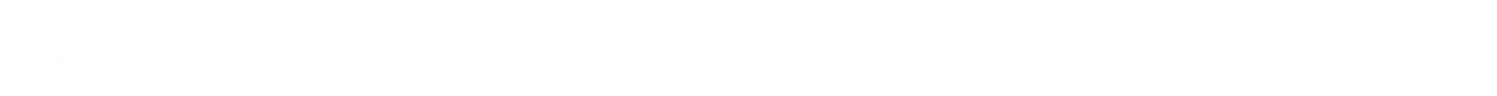【SEO記事作成】業者比較保存版!3位THE MARKE、2位ウィルゲート、そして1位は…?

「SEO記事作成 書き方」で上位に出る記事は、一見似ていても構成・実践性・費用感が大きく異なります。
本稿は、2025年10月時点の上位10社(媒体含む)を読み比べ、書き方の質と料金面の傾向をセットでレビューしました。
また、どのサービスを選ぶべきかは、企業の運用体制や組織内の人材スキルレベルによっても大きく異なります。
たとえば、社内にSEO担当者やライターがいる場合は「構成設計支援型」、外注中心の企業は「戦略+制作一括型」が適します。
そのため本記事では、各社の特徴だけでなく、「どんな企業体制にマッチするか」も合わせて紹介します。
なお、料金は公開が限定的なため、「傾向(高/中/低)」+「課金形態」で明示します(詳細は各社に要見積)。
「SEO記事作成」検索結果ランキング
「SEO記事作成 書き方」で検索した際に上位表示される10社を、構成・実践性・費用感の3軸でレビューした比較表です。
| 順位 | サイト/企業 | 記事の強み(要約) | 料金傾向 | 課金形態の例 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1位 | Keywordmap | 構成〜文体まで具体。再現性が高い。 | 中 | 記事単価/都度見積 |
| 🥈2位 | ウィルゲート | 戦略×執筆を体系化。法人運用に適合。 | 中〜高 | 月額/記事単価/都度見積 |
| 🥉3位 | THE MARKE | ライター実務に直結。手法が具体。 | 中 | 記事単価/都度見積 |
| 4位 | RankQuest | 6ステップで体系化しやすい。 | 中 | 記事単価/都度見積 |
| 5位 | WACUL | 構成設計・導線に強み。 | 中〜高 | コンサル月額/都度見積 |
| 6位 | MediaReach | PREP等の実務手法が豊富。 | 低〜中 | 記事単価/都度見積 |
| 7位 | LeadNine | 原則集で網羅。教育用途に良。 | 低〜中 | 記事単価/都度見積 |
| 8位 | Molts | 設計思考に強い。編集者向け。 | 中 | 構成設計費/記事別見積 |
| 9位 | WITH TEAM | 体制・品質管理の明確化。 | 中 | 記事単価/パッケージ |
| 10位 | c-blog(Cone) | 入門向けで平易。 | 低〜中 | 記事単価/都度見積 |
※本ランキングは2025年10月時点の独自比較に基づく編集部所感です。
モタラス編集部が見た!各社記事レビュー
「SEO記事作成 書き方」で上位表示された各社コンテンツを、構成の論理性・実践性・読者誘導力の3観点(+料金傾向)で分析。
本レビューは検索結果の第10位から第1位へ向かう順番で掲載しています。
第10位:c-blog(Cone)
SEO入門的な解説中心。初心者にも読みやすく、基礎理解向け。
- 強み:専門用語を避け、初学者にもわかりやすい。
- 弱み:実践的な構成やリード設計の具体性に欠ける。
- 料金傾向:低〜中/記事単価制(都度見積)
💡これからOM立ち上げの小規模事業者、SEO基礎を掴みたい担当者。
第9位:WITH TEAM(Radineer)
分業体制重視の品質管理型。制作フローの透明性が高い。
- 強み:制作体制・チェックフローが明確。
- 弱み:「SEO記事作成ノウハウ」の深度は浅め。
- 料金傾向:中/体制パッケージ制・記事単価制
💡チーム外注したい広報部門、納期安定重視の制作会社。
第8位:Molts
編集者視点の「構成→執筆→最適化」を設計思考として体系化。
- 強み:骨格・導線設計に優れる。上流設計重視。
- 弱み:文体調整や表現ノウハウは軽め。
- 料金傾向:中/構成設計費+記事制作別見積
💡編集経験者が社内におり、外部と構成設計を磨きたい中堅企業。
第7位:LeadNine
「SEO記事の書き方19原則」。教育・理論型コンテンツ。
- 強み:体系的で社内教育・新人研修に最適。
- 弱み:実践事例が少なく、現場適用には補足が必要。
- 料金傾向:低〜中/記事単価制
💡SEO教育を内製化したい組織、研修教材を探すマーケ部門。
第6位:MediaReach
PREP法・一次情報活用など実務ライティング手法を具体化。
- 強み:現場の手が動く具体性。
- 弱み:記事全体のストーリー性は弱め。
- 料金傾向:低〜中/記事単価制
💡個人ライター育成中の編集長、スモールチーム運用の企業。
第5位:WACUL
データ思考で構成最適化。構成フェーズ特化の実用記事。
- 強み:構成分析・内部導線設計が明確。
- 弱み:表現面は軽い。
- 料金傾向:中〜高/月額コンサル・構成支援
💡既に制作チームがあり、構成精度や分析思考を高めたい部門。
第4位:RankQuest
SEO記事作成を6ステップで体系化。E-E-A-T要素も網羅。
- 強み:全体構成が整理され、中級者に向く。
- 弱み:深掘りは浅く、高度案件には物足りない。
- 料金傾向:中/記事単価制
💡外注管理を担当する社内マーケ。体系を整理したいが費用は抑えたい層。
第3位:THE MARKE
タイトル・リード・本文の書き方を実務的に解説。再現性が高い。
- 強み:PREP/タイトル設計/段落構成が具体。
- 弱み:内部リンク・サイト構造への言及は薄い。
- 料金傾向:中/記事単価制
💡中小企業の自社実践。リード改善や文章構成を磨きたい担当者。
第2位:ウィルゲート
戦略・構成・執筆・リライトを一気通貫で指南。法人SEOの定番。
- 強み:戦略×執筆の融合。E-E-A-Tを包括。
- 弱み:情報量が多く初学者にはやや難。
- 料金傾向:中〜高/月額・記事単価制
💡BtoB企業の本格導入・長期運用体制の構築を目指す層。
第1位:Keywordmap
構成・見出し・文体を完全分解。SEO記事の王道を体系化。
- 強み:読みやすさ×検索意図の両立。実務者に最適。
- 弱み:上流施策(外部リンク等)は別枠扱い。
- 料金傾向:中/記事単価制(都度見積)
💡内製チームがあり、E-E-A-T強化と構成テンプレの最適化を図りたい場合。
上位3社の差分分析:構成・再現性・内部構造の違い
上位3社はいずれも「構成設計×実践性」で高評価ですが、H2/H3構成・キーワード分布・本文尺など内部構造に差があります。
| 比較項目 | Keywordmap(1位) | ウィルゲート(2位) | THE MARKE(3位) |
|---|---|---|---|
| 構成の完成度 | H2/H3連携が自然。内部リンク意図明瞭。 | 戦略・E-E-A-Tの厚み最上位。長文傾向。 | 段落設計明快。サイト構造連動は軽め。 |
| H2/H3 構成数 | H2×8・H3×4 | H2×7・H3×3 | H2×6・H3×3 |
| 主要キーワード数 | 約45語(上位KW8種を自然分散) | 約38語(構成に沿って整理) | 約30語(集中型) |
| 本文ボリューム | 約6,800字 | 約7,200字 | 約5,500字 |
| 再現性 | テンプレ化しやすく誰でも再現可。 | 中〜上級者向け(戦略理解前提)。 | 入門〜中級者向け(即実践可)。 |
| 適用範囲 | BtoB/BtoC汎用。 | 中〜大規模運用体制向け。 | 小規模チーム・個人運用向け。 |
※2025年10月15日時点、日本国内Chromeシークレット(非ログイン)環境で取得したデータを基にした参考値。順位・数値は変動します。
総括:成功パターンの共通項
SEO上位には、明確な「型」と「意図」があります。以下の3点が共通項です。
- 検索意図の可視化:「誰の・何の意思決定を助けるか」を先に言語化。
- 構成設計の一貫性:タイトル→リード→H2/H3→本文→内部リンクを一直線で結ぶ。
- E-E-A-T+一次情報:体験・実例・引用・監修を自然に組み込む。
🔍 Googleが重視する評価ルール
- Helpful Content:読者の課題を最優先に解決しているか
- E-E-A-T:経験・専門性・権威性・信頼性の4軸
- 構造化データ:検索エンジンが理解しやすい設計か
- 内部導線:次の行動(お問い合わせ・購入)を促す流れ
【無料診断】あなたのSEO記事、Google評価軸と上位競合との差分を可視化
上記の「成功パターン」やGoogle評価ルールに、あなたのSEO記事がどれだけ適合しているかをモタラス編集部が分析。
さらに、検索上位の記事(自社より上位の3記事)と比較し、「構成・キーワード・内部リンク・E-E-A-T」などの差分を定量化します。
- 対象:1記事(構成・キーワード設計・E-E-A-T・競合比較)
- 分析内容:上位3記事との比較レポート+改善優先度チェックリスト(PDF納品)
- 所要期間:2〜3営業日/営業行為・勧誘いっさい無し
※比較対象は指定キーワードの検索結果上位(2025年10月時点)をもとに解析。分析環境:Google Chrome/シークレット(日本国内・東京IP)。
まとめ:motaras Rogic — モタラスが考えるSEO記事の本質
① 検索意図の翻訳
読者の検索目的を「企業の言葉」に変換。単なる記事制作でなく、意図の翻訳からスタート。
② 導線設計の一貫性
タイトル→本文→CTAまで、読者の心理を切らさず次行動へ導くストーリー設計。
③ 成果を生む構造化
検索エンジンと読者双方が理解しやすい構造に整える。記事は“作る”でなく“成果の仕組み”。
🔍 自社のSEO記事の段階を把握したい方は、無料のSEO記事診断をご利用ください。
よくある質問(SEO記事作成の比較・選び方)
Q. 上位記事のどれを参考にすべき?
A. 目的と体制次第。内製は1位/3位の再現性、外注主導は2位の運用一貫性が合います。
Q. 「ブランド名+ビッグキーワード」でのタイトル設計は有効?
A. 有効です。上位ブランドの指名検索の“取りこぼし”を拾い、比較・代替ニーズを獲得できます。
Q. 記事はどの頻度で更新すべき?
A. 3か月ごとに差分更新(順位・構成・字数・内部リンク)。更新履歴を明記すると評価が安定します。